| �g�b�v�����C�t�v�������k���������̎��O���� |
|
�@�@�@�`�q�̂��Ȃ��v�w�̗�`
�@�@�@�`�����҂̗�`
�@�@�@�`�V���O���̗�`
|
|
- �P�D�����ł���l�Ƃ��̎����͈ꉞ���܂��Ă��邪�A�⌾�Ŏw����ł���B
- �e�����S����Ƒ����l�͎q�ł��B�푊���l�i���S�����l�j�̔z��҂������l�ɂȂ�܂��B
�@���ł́A�����l�ɂȂ��u�@�葊���l�v���߂Ă��܂��B
�@�葊���l���A�����ł���Œ���̎������u�@�葊�����v�Ƃ����A������@���Ō��܂��Ă��܂��B
�������A�@�葊���l��@�葊�����ɂƂ��ꂸ�A�u�⌾�v�Ŏw�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�������l�F�S���Ȃ����l�̍��Y�⌠���A�`���������p���l
�@���푊���l�F�S���Ȃ����l
���@�葊���l��
| 1�Ԗ� |
�q�i���n�ڑ��j
�@���{�q��َ��i���Y�������j�A�����O�̎q���܂܂�� |
�z��� |
���ԂɊW�Ȃ�
�����l�ɂȂ� |
| �@�@��1�Ԗڂ����Ȃ��ꍇ�͎����� |
| 2�Ԗ� |
�e���c�����i���n�����j |
| �@�@��2�Ԗڂ����Ȃ��ꍇ�͎����� |
| 3�Ԗ� |
�Z��o�� |
���@�葊������
| |
�����l�ɂȂ�鏇�ԂƐl |
�������� |
| �z��҂�����P�[�X |
��1���� |
�q
(���n�ڑ�) |
�z��� |
 |
| ��2���� |
�e
(���n����) |
 |
| ��3���� |
�Z���o�� |
 |
�q�A�e�A�Z��o������������ꍇ�́A�ϓ��ɕ����܂��B
�@���၄�z��҂Ǝq�P�A�q�Q�������l�̏ꍇ
�@�@�@�@�@�@�@�z��ҁF1/2
�@�@�@�@�@�@�@�@�q�P�@�F1/2�~1/2=1/4
�@�@�@�@�@�@�@�@�q�Q�@�F1/2�~1/2=1/4 |
 |
| �z��҂����Ȃ��P�[�X |
��1���� |
�q�i���n�ڑ��j |
�S�� |
| ��2���� |
�e�i���n�����j |
�S�� |
| ��3���� |
�Z��o�� |
�S�� |
���@�葊���l�̂Ɩ@�葊�����̗၄
�@�@�@�@�@�z��҂Ǝq�ǂ��Q�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�̂��Ȃ��v�w
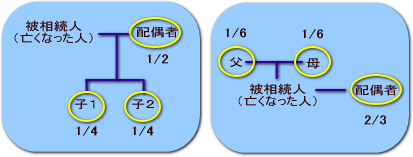
������
�@�@�@�@�e�͎��S�A�Z�̂��関����
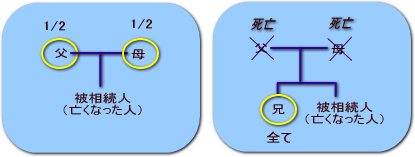
|
 �y�[�W�g�b�v �y�[�W�g�b�v |
|
- �P�D�q�̂��Ȃ��v�w�̗�
- �q�̂��Ȃ��v�w�łǂ��炩�Е����S���Ȃ����Ƃ��܂��B�z��҂͂�������l�ł���A��2���ʂ̐e����3���ʂ̌Z��o���������l�ɂȂ邽�߁A�ȉ��̃p�^�[�����l�����܂��B
|
�@�z��҂Ɛe�i�z��҂̋`����j
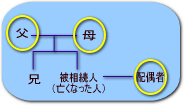
�@�@�@ |
���g���u���̗\����
�E�}�C�z�[����Ԃ͒N�̂��́H
�E�`����Ɠ������Ă�����A���̂܂Z�ށH
�E����͂ǂ�����H
�E�z��҂Ƌ`�����`�Z��̊W�͗ǍD�H
�E�F�A�����̏��葱�ɋ��͂��Ă����H
�E�����̎葱���͂ǂ��炪����H |
�A�z��҂ƌZ��i�z��҂̋`�Z��j
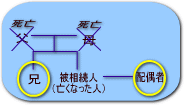
|
���g���u���̗\����
�E�}�C�z�[���͒N�̂��́H
�E�ԁA�a�����Ȃǂ͒N�̂��́H
�E�z��҂Ƌ`�Z��̊W�͗ǍD�H
�E�Z�͑����̏��葱�ɋ��͂��Ă����H
�E�����̎葱���͒N������́H
|
�B�z��҂̂݁@
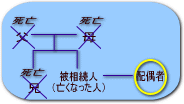
 �@�@ �@�@
|
���g���u���̗\����
�E����͂ǂ�����H
�E�����̎葱���͈�l�łł���́H
�E�푊���l���e���瑊�����Ă������̂��A���̌�͑S�Ĕz��҂̂��̂ł����́H |
 �y�[�W�g�b�v �y�[�W�g�b�v
|
- �Q�D�����҂̗�
- �q�̂���l���������čč��̌�Ɏ��S�����Ƃ��܂��B�O�Ȃ�O�v�Ƃ̎q�������l�ɂȂ邽�߁A�����͈ȉ��̂悤�ȃp�^�[�����l�����܂��B
|
�@�q�����闣���҂ŁA�č�����q������

|
���g���u���̗\����
�E�q�`�͑O�Ȃ̑����l�ɂ��Ȃ�B����ɐ��т�����Ȃ炻���Ƃ̂Ȃ���͂���H
�E�z��҂Ƌ`����B�Ƃ̊W�͗ǍD�H
�E���ɔz��҂����S�����Ƃ��͎q�P�����������l�ɂȂ邩��A����̔푊���l�̍��Y�̑����͎q�`�ɍs���Ȃ����ǖق��Ă�����́H
|
�A�q������ғ��m�̍č�
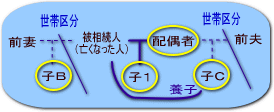
 �@�@ �@�@
|
���g���u���̗\����
�E�q�b�͑O�v�̑����l�ɂ��Ȃ�B����ɐ��т�����Ȃ炻���Ƃ̂Ȃ���͂���H
�E�z��҂͎q�a�ɉ�������Ƃ�����H
�E�Ƃ�ԁA�a�����Ȃǂ͒N�̂��́H
�E�z��҂Ƌ`����B�Ƃ̊W�͗ǍD�H
�E���ɔz��҂����S�����Ƃ��͎q�P�Ǝq�b�������l�ɂȂ邩��A����̔푊���l�̍��Y�̑����͎q�a�ɍs���Ȃ����ǖق��Ă�����H
|
 �y�[�W�g�b�v �y�[�W�g�b�v
|
- �R�D�V���O���̗�
- �����Ō����V���O���Ƃ́A�����҂Ǝ��ʁi�č��Ȃ��j�E�����ҁi�č��Ȃ��j�Ŏq�����Ȃ��҂������܂��B�e��Z��o��������Ȃ瑊���l�ƂȂ�܂����A�N�����Ȃ��Ȃ�A����͂���őΏ����K�v�ł��B
�����͈ȉ��̂悤�ȃp�^�[�����l�����܂��B
|
�@���ʂ̌�A�č��Ȃ��B
�@�`��������E������B
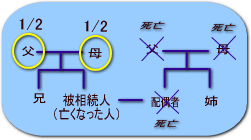
|
���g���u���̗\����
�E�z��҂����Ƃ��瑊�����Ă������K�����A���菄���ĉł���̋`����ւƍs���������ƂɂȂ�B�o�͖ق��Ă�����̂��H |
�A�����l�����Ȃ�
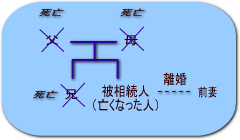
|
���g���u���̗\���z��
���������N����Y�������p���̂��A���͏������Ă����̂��B
|
 �y�[�W�g�b�v �y�[�W�g�b�v
|
|
- �P�D�⌾������
- �����l�͕K�������u�@�葊���l�v�Ƃ͌���܂���B�w�⌾�x������Ă����Ζ@�葊���l�ȊO�𑊑��l�Ɏw�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
|
���⌾�̌��ʁ�
�⌾�������Ȃ瑊���l�́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�⌾�����邨������
�z��҂ƌZ��o���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z��҂����������l�ɂȂ��
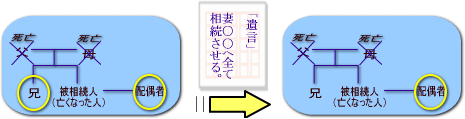
���⌾�̃����b�g��
�@�E�}�C�z�[����a���Ȃǂ��Z�ƕ����Ȃ��ėǂ����}�C�z�[���ɌZ�̖��`�������Ă������ς�
�@�E������̂��낢��Ȏ葱���ɁA�Z�̃n���R��������Ȃ����ς킵�����Ȃ�
�@�E�N�ɉ�������ǂ��̂������m�ɂȂ��Ă��遨���_�ȑ������������
|
���⌾�̎�ށ�
�⌾�͂ǂ̂悤�ɏ������ɂ���āA��ȂR��ނ̓�����I��ł���܂��B
| |
���M�؏��⌾ |
�����؏��⌾ |
�閧�؏��⌾ |
�^�C�v��
���� |
�E�z��҂ɑS�đ���������
�E�V���O��
�E��������m������
�E�����l��1�l���� |
�E�����ȊO�̎��Y������
�E�◯���Ȃǂ̒m�����Ȃ�
�E�s�����S�z |
�E�⌾���k���ƃg���u���ɂȂ�
|
| ���@�� |
�܂��͈⌾������Ă��������l�Ƀs�b�^���B3�̒��ł͈�Ԏ�y�ƌ����� |
�s���̂Ȃ��⌾���c�������l�ɂ̓s�b�^�� |
���g��N�ɂ��m��ꂸ�Ɏc�������l�Ƀs�b�^�� |
| ���@�� |
�Ȃ����Ɏc���ȂǁA�ȒP�Ȃ��̂ł���������ɂł������� |
���q�������̂����ؐl�������L���Ă���邽�ߕs�����Ȃ� |
���̈⌾�͔閧������Ȃ����A�閧�؏��⌾�͉������������������S�z�Ȃ� |
| �Z�@�� |
�E�����ŏ������ߌ��t������Ȃ��ȂǕs�����S�z
�E�����̋��������
�E���g���m���Ȃ��ۏ͂Ȃ�
|
�E�ؐl�Q�l�̗�������K�v
�E�����~�̔�p��������
�E���e���ؐl����k��Ȃ��ۏ͂Ȃ� |
�ۊǂ͌��ؐl����ł��Ă���邪�A���g�̕s���̋���͎��M�؏��ƕς��Ȃ� |
|
- �Q�D�u�⌾�v���m���Ɏ��s���Ă����l�����߂Ă���
- �⌾���c�����Ƃ��Ă��A�����l�������ɏZ��ł�����A�Ȃ��Ȃ����R�ɓ����Ȃ��ꍇ�́A�⌾�̂Ƃ���ɍ��Y����葱���Ȃǂ́u�����v���ʂ����Ă����l���K�v�ł��B
���ɂ́A�Z���̓��N����l�̗͂��������߁A�⌾�����Ĉ�Y�������c������Ă��܂������ȂƂ��́A��͂�����Ɏ葱����i�߂Ă����l�����߂Ă����ƈ��S�ł��傤�B
�����̂��Ƃ����Ă����l���u�⌾���s�ҁv�Ƃ����A�⌾�̒��Ŏw�����邱�Ƃ��ł��܂��B
|
���⌾���s�҂ɂȂ��l��
�j�Y���Ă���l��s���ǂ̐l�A�����N�҈ȊO�ł���ΒN�ł��ǂ��ł��B�z��҂ɂ��邱�Ƃ͂������A�M���ł���F�l�A���߂��̂e�o�E�s�����m�E�i�@���m�E�ٌ�m�A�M����s�ł����\�ł��B
���⌾���s�҂ւ̕�V��
�N�Ɉ⌾���s�����肢����ɂ��Ă��A��ԂƎ��Ԃ�������܂�����A����Ȃ�̕�V�ƌ�ʔ��E�X���㓙�̎���͑����l�����S���܂��傤�B
��p�͂��݂��̘b�������ɂ��̂Ńn�b�L�����܂��Ă͂��܂��A�ȉ����Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
| �⌾���s�� |
��V�̎Q�l�z |
| �ٌ�m |
400,000�~�O��(24.3%)�A1,000,000�O��(23.1%)�A600,000�~�O��(20.2%)
�@(���{�ٌ�m�A����w�ݹ�Č��ʂɂ��ƂÂ��s���̂��߂ٌ̕�m��V�̖ڈ�) |
| �M����s |
�Œ��V�z1,575,000�~�`�������Y�]���z�ɂ�茈��
�@�i�O�H�t�e�i�M����s�j
�Œ��V�z1,050,000�~�`�������Y�]���z�ɂ�茈��
�@�i�Z�F�M����s�j |
| �s�����m |
����333,294�A�ŕp�l200,000�~
�@�i���{�s�����m��A����w�s�����m��V�z���v�i����18�N�Łj�x�j |
| ̧��ݼ�٥����Ű |
�Œ��V�z300,000�~�`
�@�i�e�o�I�t�B�X���C�Y�̕�V�K��j |
| ����L�̂ق��A�⌾���s�ɕK�v�ȁA�s���Y�o�L�Ɋւ���o�^�Ƌ��ł�i�@���m�萔���A�ːГ��{���̎��萔���Ȃǂ̎���͕ʓr�K�v�ł��B |
|
| �@�@ �@ |
|
�������k�����\��

��PC�p�����k��t�t�H�[����

���g�їp�����k��t�t�H�[����

���k�C���O�̕��͂����炩��ǂ�����

�M�������g�e�o���S���Ή����܂�
|
 �y�[�W�g�b�v �y�[�W�g�b�v |
�z�[���@�@�T�C�g�}�b�v�@�@�������̂��ē��@�@���₢�������@�@�v���C�o�V�[�|���V�[
Copyright 2009 Toshio Nakatani |