試験
範囲 |
範囲の細目 |
過去問例
(正解) |
09年度 |
08年度 |
07年度 |
06年度 |
05年度 |
04年度 |
03年度 |
02年度 |
| 3回 |
2回 |
1回 |
3回 |
2回 |
1回 |
3回 |
2回 |
1回 |
3回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |

|
税法体系 |
税金を直接税と間接税に区分すると、所得税、法人税、相続税、贈与税、固定資産税、地価税はいずれも直接税である。
(○) |
|
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
| 税の種類 |
個人の所得に対する税として所得税や住民税等があり、資産に対する税として相続税、贈与税、消費税等がある。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|

|
所得税の定義 |
|
|
|
|
|
16 |
16 |
|
|
47 |
46 |
|
|
46 |
|
|
|
16 |
|
|
16 |
| 納税地 |
日本国籍をもつ個人は、非居住者であっても、海外で生じた所得を含め、その全ての所得に係る所得税の納税義務を負う。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
| 収入金額 |
所得税の計算における収入金額は、その年において収入すべきことが確定した金額であり、未収のものも含む。
(○) |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必要経費 |
事業所得の必要経費の計算上、平成10年4月1日以後に取得した建物(鉱業用減価償却資産を除く)の減価償却方法は、定額法のみであり、定率法は認められない。
(○) |
|
49 |
|
|
|
17 |
|
|
|
47 |
47 |
|
47 |
|
47 |
|
|
|
|
|
| 非課税所得と課税所得 |
公的年金のうち、遺族が支給を受ける遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金は、いずれも所得税は課されない。
(○) |
|
|
|
|
46 |
|
|
46 |
46 |
17 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
46 |
|
| 総所得、課税総所得金額等の概略 |
所得税は、個人が1暦年間に得た所得に対して課される国税であり、この場合の所得とは収入金額と同額である。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
| 納付税額の計算 |
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
46 |
|
|
|
| 租税特別措置法による特別な税額計算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 総合課税と分離課税 |
所得税は原則として総合課税であるが、利子所得、退職所得、山林所得、土地・建物等の譲渡所得などのように分離課税とされるものもある。
(○) |
|
|
16 |
|
47 |
|
47 |
16 |
|
|
46 |
16 |
|
|
46 |
|
17 |
18/
46 |
|
17 |

|
利子所得 |
定期積金の給付補てん金は、利子所得に該当し、所得税の総合課税の対象とされる。
(×) |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 配当所得 |
配当所得については、収入そのものが配当所得の収入金額となり、配当所得を生ずる株式を借入金により取得している場合でも、その負債の利子の額を配当等の収入金額から差し引くことはできない。
(×) |
|
|
17 |
|
|
47 |
16 |
|
48 |
|
|
|
17 |
|
17 |
|
|
|
|
20 |
| 不動産所得 |
所得税において、借地権の設定により対価を受け取った場合、対価として受け取る権利金等の大きさにかかわらず、その所得は、不動産所得とされる。
(×) |
|
18 |
25 |
17 |
|
|
|
|
|
|
24 |
48 |
|
|
18 |
16 |
|
|
|
|
| 事業所得 |
所得税において、事業所得の金額は総収入金額から必要経費を差し引いて計算される。減価償却費は必要経費の一つであり、機械の減価償却方法は定額法に限定されている。
(×) |
|
19 |
|
18 |
|
|
|
18 |
|
16 |
|
|
16 |
|
47 |
17 |
|
|
|
|
| 給与所得 |
給与所得は、給料、賃金、賞与ならびにこれらの性質を有する給与等に係る所得をいい、通常、収入金額から給与所得控除額を控除した金額が、給与所得の金額とされる。
(○) |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
16 |
|
18 |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
| 譲渡所得 |
土地・建物等の譲渡所得金額の計算における建物の取得費には、資産の取得に要した金額(減価償却費相当額控除後)のほか、設備費、改良費の額、取得から売却までの毎年の維持管理に要した費用が含まれる。
(×) |
|
|
48 |
|
17 |
|
21 |
|
|
|
|
18 |
18 |
|
|
16/
47 |
47 |
|
|
|
| 一時所得 |
|
|
|
|
|
|
49 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
46 |
| 雑所得 |
本人が受け取る国民年金などの公的年金による収入は雑所得となるが、過去の勤務先から支給される年金による収入は給与所得となる。
(×) |
|
50 |
|
19 |
|
18 |
18 |
|
49 |
|
|
46 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
| 退職所得 |
所得税における退職所得については、退職手当等の収入金額の全額を課税対象とするのではなく、勤続年数に応じ、収入金額から1年あたり50万円の控除額を差し引いた後の金額の3分の1相当額を退職所得の金額としている。
(×) |
|
|
47 |
|
|
|
|
47 |
17 |
18 |
48 |
47 |
|
46 |
|
|
|
47 |
17 |
|
| 山林所得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
損益通算の考え方とその順序 |
青色申告者に限り、損益通算の結果、【 損失】の金額が生じた場合、一定の要件のもとに、前年分の所得税の額のうち一定の金額の繰戻還付を受けることができる。
(純) |
|
20 |
18 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
| 所得の総合と損益通算の仕組み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 損益通算ができる所得とできない所得の区別 |
所得税の計算において事業所得の損失を一時所得の金額と損益通算する場合、その事業所得の損失を差し引くときの一時所得の金額は、特別控除(最高50万円)の控除後の金額で2分の1を乗ずる前の金額である。
(○) |
|
17 |
|
|
48 |
50 |
19 |
|
18 |
49 |
|
|
19 |
|
|
18 |
48 |
48 |
47 |
18 |

|
控除の種類とその順序および手続き |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 各種所得控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
47 |
| 雑損控除 |
Aさん保有の居住用家屋が火災により焼失した。この損失の金額(保険金で補てんされた部分を差し引いた金額)が300万円である場合、Aさんの総所得金額等が700万円であるとすれば、損失金額である300万円全額がその年の雑損控除の対象になる。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
| 医療費控除 |
納税者であるAさんが自分自身、またはAさんと生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、各人の所得の金額にかかわらず、一定の要件を満たせば、その年中に支払った医療費はAさんの医療費控除の対象となる。
(○) |
|
|
20 |
|
49 |
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
48 |
|
|
19 |
|
|
19 |
| 社会保険料控除 |
納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、原則として、その支払った金額の全額が社会保険料控除の対象となる。
(○) |
|
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 小規模企業共済等掛金控除 |
所得税において、納税者が小規模企業共済掛金等を支払った場合は、小規模企業共済等掛金控除として、その年に支払った掛金の全額が所得控除の対象となる。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
| 生命保険料控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 損害保険料控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
| 配偶者控除 |
納税者と生計を一にする青色事業専従者である配偶者は、青色事業専従者給与の額が103万円以下で他に所得がなければ、控除対象配偶者となるので、配偶者控除の適用を受けることができる。
(×) |
|
47 |
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
49 |
18 |
|
| 配偶者特別控除 |
平成16年分以後の所得税において、生計を一にする配偶者がいる納税者は、その配偶者が控除対象配偶者ではないとき、一定の要件を満たせば配偶者特別控除を受けることができる。
(○) |
|
|
|
20 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
| 寄付金控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 障害者控除 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老年者控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寡婦(夫) 控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勤労学生控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 扶養控除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
| 基礎控除 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
配当控除 |
所得税において公募の株式投資信託(特定株式投資信託を除く)の収益の分配金は配当所得とされ、確定申告すれば配当控除が受けられる。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
49 |
20 |
| 住宅借入金等特別控除 |
住宅借入金等特別控除は、所得金額から一定金額を控除するもの(所得控除)で、所得税額から一定金額を控除するもの(税額控除)ではない。
(×) |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
50 |
|
|
|
22/
49 |
|
50 |
46 |
|
50 |
|
48 |
| 定率減税の計算と概略知識 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
19 |
49 |
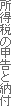
|
源泉徴収制度の対象となる所得・徴収額 |
個人が得る割引金融債の償還差益に対しては、発行時に雑所得として18%の源泉徴収が行われ、課税関係が終了する。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
0 |
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
| 支払調書、源泉徴収票、徴収義務者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 源泉徴収票の見方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 確定申告 |
年間給与収入1500万円の給与所得者が、給与所得のほかに原稿料による所得が30万円ある場合には、確定申告書の提出義務がある。
(○) |
|
|
19/
49 |
|
20 |
|
49 |
|
|
20 |
|
|
|
49 |
|
|
|
19/
20 |
50 |
|
| 青色申告 |
青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は、その給与の合計所得金額が38万円以下であっても、所得税の配偶者控除における控除対象配偶者にはならない。
(○) |
|
48 |
|
48 |
|
20 |
|
50 |
|
|
50 |
|
|
18 |
48 |
|
|
|
|
50 |
| 納付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 異議申立、審査請求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
納税義務者 |
所得税の源泉徴収義務者は、給与等の支払いの際に源泉徴収した源泉徴収税額を、納税義務者に代わって、原則としてその支払った日の翌月10日までに納付する。
(○) |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 均等割と所得割、利子割 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税計算との相違 |
所得税と個人住民税の所得控除において、その金額が同額である控除には、【 控除】がある。
(社会保険料) |
|
|
|
49 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|

|
事業税と納税義務者 |
個人事業税は、個人の営む一定の事業についてその所得に課税されるものであり、不動産の貸付による所得についても、貸付が一定の規模以上になると課税対象になる。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| 所得と税額の計算 |
個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として【 】の事業主控除を控除する。
(290万円) |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 申告と納付 |
個人事業税の申告は、所得税の申告と同様、翌年の3月15日までであるが、所得税の確定申告をした者は、原則として個人事業税の申告をする必要はない。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|

|
消費税(※) |
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、原則として消費税の課税対象となる。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
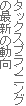
|
最新のタックスプランニング |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|