試験
範囲 |
範囲の細目 |
過去問例
(正解) |
09年度 |
08年度 |
07年度 |
06年度 |
05年度 |
04年度 |
03年度 |
02年度 |
| 3回 |
2回 |
1回 |
3回 |
2回 |
1回 |
3回 |
2回 |
1回 |
3回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
2回 |
1回 |
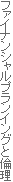
|
FPの社会的ニーズ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
1 |
1 |
|
| FPの社会的役割 |
ファイナンシャルプランニング技能士は、国家資格として定められている名称独占資格であり、法律により固有の業務を独占的に行うことが認められている。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
1 |
1 |
|
FPの職業的原則
(顧客利益・守秘義務) |
ファイナンシャル・プランナーは、特定の顧客の資産や家庭事情を他の顧客に説明しても問題はない。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
1 |
1 |
|
|
31 |
31 |
1 |
|
|
|
1 |
| 税理士法 |
税理士の資格を有しないものは、具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない。
(○) |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
31 |
2 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
2 |
|
| 保険業法 |
ファイナンシャル・プランナーは、金融商品全般にわたる知識を有すると認められているため、生命保険募集人でないファイナンシャル・プランナーが、生命保険を勧誘したり、販売しても、保険業法に規定されている禁止行為には該当しない。
(×) |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 投資顧問業法 |
資産家の顧客Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBを信頼していて、「Bの判断により一定金額の範囲内で個別株式や投資信託に投資してほしい」と報酬を支払って資産運用を任せている。Bも、預金、保険、不動産などとあわせた投資結果を1ヶ月単位でAさんに報告しているので、Bの行為はコンプライアンス上、問題になることはない。(×) |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 弁護士法 |
ファイナンシャル・プランナーのA氏は、遺産分割協議や遺言等の個別・具体的な相談を受けた場合、弁護士などの専門家を交えて対応し、相談内容については専門家より回答してもらっている。
(○) |
|
1 |
|
|
1 |
|
4 |
|
2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
| 関連法規全般 |
ファイナンシャル・プランナーは、法令等を遵守することはもちろんであるが、それ以上に高い倫理が必要とされ、当然のことながら、顧客情報の秘密を保持すること、顧客の立場に立ったプランニングをすること、税務書類の作成や法律相談などの専門家が行う業務を顧客サービスとして代行することが求められる。(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
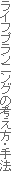
|
ライフプランニングの目的と効用 |
ファイナンシャル・プランナーが顧客のライフデザイン(生きかた)を踏まえたライフプランの実現を支援するためには、マネープランの提案が欠かせない。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 各ライフステージにおける一般的テーマ |
会社員から自営業者になると、一般的に従前と比較して公的年金や健康保険などが手薄になるため、加入している保険の見直しなどを検討する必要性が増すといえる。
(○) |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
34 |
|
| ライフステージ別資金運用 |
近い将来必要となる子供の教育資金を準備しようとしている人に対して、安全性と流動性重視型の金融商品へ投資するようアドバイスをする。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4/5 |
|
|
| 顧客情報等各種の情報の収集・把握方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ライフイベント表の作成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャッシュフロー表の作成 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
2 |
|
31 |
32 |
|
|
31 |
|
|
|
|
| 個人のバランスシートの作成 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提案書の作成
(必要保障額・係数の意味) |
Aさんは、60歳から85歳までの25年間、元金を一定利率で運用することにより、年間150万円ずつ年金を受け取りたいと考えている。この場合において、60歳の時点で必要とされる元金額は、年金現価係数により算出することができる。
(○) |
|
31 |
|
31 |
31 |
32 |
34 |
2 |
|
|
3 |
32 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|

|
社会保険制度の全体像について概略 |
社会保険制度には、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険および介護保険がある。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
32 |
|
4 |
4 |
| 公的医療保険の全体像 |
健康保険などの職域保険の被保険者およびその被扶養者、生活保護を受けている世帯を除いて、市町村または特別区の区域内に住所がある人は、全員が国民健康保険の被保険者となる資格を有するが、加入するか否かは任意である。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
31 |
2 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 健康保険の仕組み |
健康保険は、事業所単位の強制加入が原則であるが、会社などを退職して被保険者の資格を失った場合でも、要件を満たせば被保険者として一定期間は継続することができる。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者という。
(○) |
|
4 |
3 |
|
34 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
31 |
|
|
| 国民健康保険の仕組み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退職者及び、高齢者向け公的医療制度 |
民間企業を定年退職した後の公的医療保険として、在職中の健康保険制度を【 年間】任意継続し、その後、国民健康保険に加入することができる。
(2) |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公的介護保険の仕組み |
公的介護保険制度においては、市町村または特別区の各区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険化入社を第1号被保険者といい、65歳以上の者を第2号被保険者という。
(×) |
|
|
|
5 |
|
|
1 |
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
|
| 公的医療制度の最近の動向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 労働者災害補償保険 |
労働者災害補償保険(労災保険)の保険者は政府で、原則として労働者を1人でも雇っている事業所は強制加入である。
(○) |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
|
| 保険給付の種類と内容 |
労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が【 】以上に及ぶ場合に支給され、その額は、休業【 】日以後、休業1日につき原則として給付基礎日額の60%相等額である。
(4)
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特別支給金制度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特別加入制度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雇用保険 |
労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が【 】以上に及ぶ場合に支給され、その額は、休業【 】日以後、休業1日につき原則として給付基礎日額の60%相等額である。
(4)
|
|
|
|
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
| 失業等給付 |
雇用保険法の求職者給付において、定年を離職の事由とする者に対する基本手当の所定給付日数の上限は、被保険者期間が20年以上あった場合は、150日である。
(○) |
|
35 |
|
|
|
|
|
3 |
5 |
3 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
5 |
| 雇用三事業 |
雇用保険は失業者のための制度であり、雇用の継続を援助・促進するための給付や能力開発の取り組みを支援する給付など、すでに雇用されている人に対する給付は、雇用保険では行われていない。
(×) |
|
5 |
5 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|

|
公的年金制度の全体像と最近の動向 |
わが国の公的年金制度における年金給付には、老齢を原因とする老齢(退職)年金、障害を原因とする障害年金、死亡を原因とする遺族年金があり、それぞれ一定の要件を満たせば給付が行われる。
(○) |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
31 |
|
| 国民年金 |
学生の国民年金保険料の納付特例は、同居している両親の前年の所得が118万円を超えないことが適用用件の一つとなっている。
(×) |
|
33 |
33 |
|
4 |
35 |
2 |
33 |
32 |
|
33 |
33 |
4 |
|
4 |
32 |
|
32 |
|
31 |
| 厚生年金保険 |
厚生年金保険の被保険者機関が25年以上あり、平成17年4月2日に60歳の誕生日を迎える男性(昭和20年4月2日生まれ)は、原則として【 歳】から特別支給の老齢厚生年金を受給できる。
(63歳) |
|
|
34 |
33/
35 |
35 |
|
32 |
32 |
31 |
33 |
|
34 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
| 共済年金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老齢給付 |
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 障害給付 |
国民年金の障害基礎年金を受けるための原則的な保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることとなっている。
(○) |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遺族給付 |
遺族基礎年金を受給するための保険料納付要件は、原則として、死亡日の前日において、死亡した被保険者の死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が2分の1以上あることとなっている。
(×) |
|
|
35 |
34 |
|
|
33 |
|
|
4 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|

|
企業年金の全体像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
確定給付型年金
(適年・厚生年金基金) |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
33 |
32 |
|
|
|
33 |
|
確定拠出年金
(企業型・個人型の仕組み) |
確定拠出年金の個人型の掛金拠出限度額は、自営業者などの国民年金の第1号被保険者、既存の企業年金および確定拠出年金(企業型)未実施の企業に勤務する国民年金の第2号被保険者ともに、その額は月額68000円である。
(×) |
|
|
|
|
5 |
|
3 |
35 |
33 |
34 |
|
|
34 |
34 |
34 |
33 |
4 |
|
32 |
32 |
| 個人年金とは |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 個人年金の分類 |
個人年金は、受け取り方法によって、一般に、被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる「終身保険」、被保険者の生死に関係なく一定期間だけ年金を受け取ることができる「有期年金」、一定期間中被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる「確定年金」に大別できる。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 各業態別 個人年金商品 |
一時払いの変額年金保険は、年金支払開始時まで、運用実績に応じた死亡保障があり、最低でも払込保険料程度の死亡保障が保証されている。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
6 |
| 財形貯蓄制度の概要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財形年金の仕組みと商品 |
財形年金貯蓄制度は、勤労者が給与天引きで積み立てた資金を原資として、60歳以降の一定期間に、年金方式または一時金方式で給付が受け取れる長期貯蓄制度である。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
5 |
|
|
34 |
34 |
|
3 |
|

|
公的年金等に係る課税の仕組み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
| 公的年金等の範囲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
| 個人年金の掛金に対する税の取扱い |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 個人年金の受取金に対する税の取扱い |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企業年金に係る税金の知識 |
老齢厚生年金や退職共済年金は、所得税の計算上、年金受給時に公的年金等控除の適用を受けられるが、厚生年金基金、税制適格退職年金、確定拠出年金については年金受給時に公的年金等控除の適用をうけられない。
(×) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
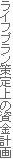
|
住宅取得の考え方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購入時の諸費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自己資金の形成プラン |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住宅取得と税金 |
土地・家屋に係る固定資産税は、毎年【 月 日】現在のその固定資産の所有者に課税される。
(1月1日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
34 |
35 |
|
| 住宅ローンの仕組み |
住宅ローンの金利には固定金利型と変動金利型とがあるが、固定金利が頼りも、市場金利の変動に応じて借入金利の見直しがおこなわれる変動金利型のほうが、金利情勢に関わらず総返済額は少なくなるため、利用者にとっては有利である。
(×) |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 種類と内容 |
住宅金融支援貴校と民間金融機関が提携して提供しているフラット35は【 】が適用される住宅ローンである。(融資実行時の金利) |
|
|
32 |
|
32 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
35 |
| 借換え |
民間住宅ローンは、公的住宅融資とは異なり、所定の要件を満たせば、金利の低いローンへの借り換えを目的とする場合でも利用することができる。
(○) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
| 繰上げ返済 |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住宅の買換え、建替え、リフォーム、
バリアフリー化等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育プランと教育費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育資金の形成プラン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
| 教育ローン・奨学金 |
国民生活金融公庫が扱う国の教育ローンは、返済終了まで固定金利が適用される。使途は学費に限定され、下宿費用や学生の国民年金保険料には充当できない。
(×) |
|
3 |
2 |
3 |
|
|
|
5 |
|
5 |
|
5 |
35 |
|
|
5 |
|
|
|
|
| 老後生活の必要資金の準備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老後資金プランの作成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老後生活のリスクとその手当て |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|

|
各種クレジットカードの種類と特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利用上の留意点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| デビットカード等新たな決済手段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 各種消費者向け無担保ローンの特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
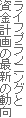
|
最新のライフプランニングと資金計画 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|